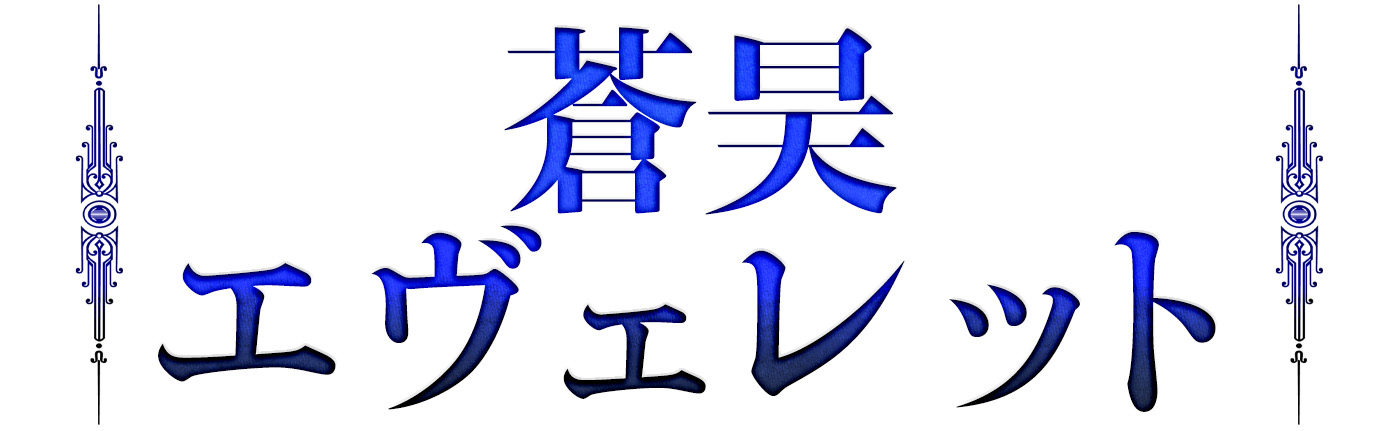

更新:不定期
企画:寂寞アルケミラ
監修:蒼77
著者:玄慧茴芹
イラスト:松田トキ
当コンテンツは寂寞アルケミラによる公式二次創作小説です。
実際の蒼77シリーズにおけるキャラクター設定との直接の関連性はございません。
© 2013 蒼77 / 寂寞アルケミラ / 玄慧茴芹 / 松田トキ
Character

| Name | ハルト - Haruto |
|---|---|
| UTAU Name | 蒼77 Code:ハルト |
| Gender | 男 |
| Age | 10 |
| Memo | 主人公。とある国の都会で一人暮らしをしていた獣人の少年。 自分で機械や物を作るのが得意。 ある日夢の中で出会った少年、レインが残していった本に載っていた異次元ワープ機を完成させてレインを探す旅に出る。 |

| Name | レイン - Rain |
|---|---|
| UTAU Name | 蒼77 Code:レイン |
| Gender | 男 |
| Age | 13 |
| Memo | ハルトの夢に現れ謎の本を残して姿を消した少年。 |

| Name | ルコ - Ruko |
|---|---|
| UTAU Name | 欲音ルコ |
| Gender | ? |
| Age | 12(自称) |
| Memo | ハルトが住んでいた街の喫茶店『珈琲屋 眠り姫』の店主。 性別不詳。好きなものは珈琲納豆。 |

| Name | ユフ - Yufu |
|---|---|
| UTAU Name | 雪歌ユフ |
| Gender | 女 |
| Age | 17 |
| Memo | 第一の国『アウル王国』に住む女の子。 |
Episode.01

摩天楼の隙間から見えた空の色は黒く澄みきっていた。
天気予報によれば今日は午後から雨が降るという事だった。晴れた日でも空は昔のようには蒼くは見えなくなっていた。どこかで聞いた話だと眼が日焼けして色褪せて見えるからだそうだ。今や科学で何でもわかってしまう。科学というのは人の味方であり、人の敵なのだろうとよく思う。
ビル街の裏路地を抜けて、僕は”家”に向かう。この”家”は数年前に見つけた廃墟を僕が開拓した所で、昔は大手企業のオフィスビルだったようだ(中に落ちていた紙や大量の机と椅子を見て僕が推測しただけなのだけれども)。廃墟とは言ったものの一人で住む環境としては最高だった。水も電気もガスも止まっておらず時々整備が必要な所以外は一人で暮らすにはもってこいな場所だった(こういう時に今まで独学で学び、作ってきた発明品が役立つのだ)。
着ていたコートを脱いで椅子の背もたれに掛ける。そしてその椅子に自ら腰を下ろした。
「あぁー……」
トーンの低い呻き声は”家”の中を反響して僕の耳に再び戻ってくる。コンクリート造りの室内ではよくある事だ。目をぎゅっと瞑り、力を抜くと目疲れていた事がよく分かる位の痛みを感じた。
「ずいぶんお疲れなんだね、ハルト」
さっきの呻き声とはまた別の声がした。後ろを振り向くと見慣れない男の子が一人立っていた。僕より三つか四つか年上だろうか。僕より大人びて見える。
「君は、誰?」
当然僕は彼に問う。誰も来るはずの無い”家”に人が来るなんてありえない。
「僕はレイン」
レイン、と名乗る男の子はそう答えた。
「何でここにいるの?」
僕はまた彼に問いた。
「……君は本が好きなんだね」
彼は部屋の隅を指差して僕に言う。その指差す先には僕が今まで読んできた本が詰まれているのが見える。
「うん。大好きだよ」
そう答えると彼は
「僕からの、プレゼント」
と一言呟き何処からともなくある一冊の本を取り出し僕に手渡した。
「また、会えるといいな」
彼はそういって”家”の外へと出て行った。
いつの間にか寝てしまったのだろうか、気が付けば陽は落ちていて”家”の外は完全に暗くなっていた。僕は重い腰を持ち上げて薄暗い部屋の電気を付け再び椅子に戻ろうとした時、戦慄した。デスクの上に、夢に出てきたあの本が置かれていたのだ。

Episode.02

人には時として、予想外な事が起きるという。
それは”嬉しいこと”であったり、あるいは”悲しいこと”であったり。
そうでなければ、”辛いこと”や”楽しいこと”であったり。
ところで、僕にも”予想外な事”が起きたことがあった。言い表すならそれは、"驚くべきこと"というのがもっとも相応しいんじゃないだろうか。
あれは夢だったのか、現実だったのか。でも。
「なんで……ここに本が……!?」
正直、夢だと思っていた。それなのに今、"本"は僕のデスクの上ちゃんとある。僕は驚きの余り床に座り込んでいた。
僕は夢の中で彼に出会ったはずだった。でも現に、此処に、こうして"本"はあった。
夢と現実の区別がつかなくなる……。そんな感覚に、僕は今まさに陥っていた。
彼が残していった(と思われる)本は、僕の部屋にある長編小説と同じ位の厚みを持っていた。高価なものなのだろうか、その作りは中世の古書を思わせるもので、物々しい表紙には『異次元ワープ機の作り方』と、とても胡散臭く書かれていた。
「……うそくさ」
率直な感想を一人呟きながら、とはいえ、僕は本の扉に手をかける。
冒頭の概論を読むに、この本は確かに『異次元ワープ機』の作り方について記されたものの様だ。まず書かれていたのは、どこかの国の物理学者が確立した、多世界解釈についての数学的解説。次いで、その多世界解釈の理論を基に設計した異次元ワープ機、つまり異次元空間を渡り歩く為の機械の作り方が、そこでは語られていた。
さすがに複雑な数式が連なっていたけれど、僕が解けないほどのものでもない。それゆえ、僕はその数式を検証してみようと思い立った。
デスクの引き出しからレポートパッドを取り出す。数式に間違いがないか改めてみる訳だ。
僕は本を広げ、ペンを取った。
そのとき。
ひらり、と一枚の紙が本のページの隙間から滑り落ちた。
「……なんだ、これ?」
床に落ちた紙はごく普通の二つ折りにされた綺麗な便箋だった。
紙の中で凛と咲く紫陽花の絵は花はまるで活きていた頃の紫陽花をそのまま閉じ込めたか、と思う位に綺麗だった。便箋を拾い上げた僕はそれを静かに開いた。
その便箋には一言
――君が来るのを待っているよ、ハルト
とだけ綴られていた。
Episode.03

翌朝、僕は少し遅めに起きた。あの後僕は”異次元ワープ機”の本を一通り読み終え、開発に必要なものをリスト化して床に就いた。開発をするにあたりかなり色々な物が必要らしく、結局リストを作り終わったのは大体三時過ぎくらいだったと思う。
カーテンを開けると昨日とは打って変わって、雲ひとつ無い快晴だった。見上げれば摩天楼の隙間から微かに空の蒼が見えた。僕は一つ、大きくあくびをしてから服を着替え始めた。
商店街に出ると、朝から買い物をする人で賑わっていた。主婦の方はもちろんのこと、若いカップルや親子連れの夫婦。様々な人がこの商店街に訪れ、買い物をしていた。
その商店街のはずれにこじんまりとした喫茶店がある。”珈琲屋 眠り姫”。こげ茶色の木の板に白いペンキで描かれた看板は、何処か、昔の居酒屋を思わせる造りである。この店は 僕がこの街に来てからよくお世話になっているお店で、店のドアノブを引いて中に入ると
「おお!ハルトじゃねぇか!ほら、こっちこいよ!」と”珈琲屋 眠り姫”の亭主で女の人にも男の人にも見える彼女、欲音ルコは店に入ってきた僕を優しく迎え入れてくれた。
僕は、手招きしてくれたルコさんの目の前にある少し高めの席に腰を掛けた。この椅子はルコさんが「ハルトと俺が同じ目線で話せるように」と言って作ってくれたものである。僕は静かに荷物を置いた。
「今日はどうしたんだ?ハルト。俺に会いに来てくれたのか?」
「まぁ、そんなところ。ホットミルクいただいていい?」
「はいよ。納豆入れるか?」
彼女は紅と蒼のオッドアイを光らせながら僕に問う。
「入れないで」
「おう」
彼女は少ししょぼんとして店の奥に入っていった。
彼女の好物は珈琲納豆という飲み物である。僕も一度だけ飲ませてもらったことがあるけれど、どうも口に合わずそれ以来は飲んでいない。
「おまたせ」
特徴的な黒髪のツインテールを揺らしながら店の奥から出てきたルコさんの手には僕が頼んだホットミルクのマグカップが握られていた。
「ありがと」
手渡しでそれを受け取った僕はまだ熱いままのホットミルクを少しすする。飲み込んだホットミルクの温かさが体全体に伝わるのがよく分かった。
「ねぇ、ルコさん。廃材少し見せてもらってもいい?」
「おう。構わねぇよ。またなんか作るのかい?」
「うん。少し興味深い本を貰ってね」
「ほー。まぁ、見ておいで。いつもの所に置いてあるから」
「ありがと!」
彼女はよく休みの日に街中で廃材を集めて回り店の裏に溜めている。その中には僕の発明に役立つものがよくあったりする為、それを引き取り発明品を完成させることも少なくは無い。廃材が山のように積まれているのを一見し、この中から材料を探し当てるのは一苦労だろう、と僕は一度大きく息を吸って廃材の山を漁り始めた。
Episode.04

気付けば頭の真上にあった太陽も、もうずいぶん傾いていた。必要としていた材料は全て廃材の中から入手することが出来た。これで無事異次元ワープ機が作れそうだ。僕は廃材を入れた袋を持って再び店の中に入っていった。
「お。おそかったな、ハルト。ミルク、冷めちゃってたから納豆入れといたぞ」
僕はジト目で彼女を見つめた。意味不明な行動をするルコさんはもはやギャグの一種だと思う。
「いいものはあったか?」
「うん、大収穫。もらってもいいかな?」
「おういいぜ。今度は何を作るんだ?」
僕は少し回答に多惑った。もし彼女に話をしたら、彼女は僕のことを笑うのだろうか。彼女との友好関係は崩れてしまうんだろうか。そう思うと僕は少し怖くなった。
「……異次元ワープ機」
「はーん、すげぇな。がんばれよ!」
「笑わないの?」
僕は反射的にそう聞いてしまった。
「わらう?なんで」
「だって、普通の人だったら次元を超えるなんて無理だって思うでしょ。それを子供の僕がやろうとしてるんだよ?」
彼女は少し眉間にしわを寄せて唸った後に少し間を置いて切り出した。
「人がやろうとしてる事を笑えるのはそれを出来た奴とそいつ自身だけだからな。それに、俺はお前の友達だ。友達が困ってる時は助けるし頑張ってる時は応援する。それだけだよ」
彼女は満面の笑顔で僕にそういった。もう冷めてしまって納豆が浮かんでいるホットミルクは少ししょっぱかった。
家に帰った僕は、鞄の中からルコさんのところで貰ってきた材料を床一面にばら撒きすぐに異次元ワープ機の製作に取り掛かった。本の設計図はずいぶん簡単に書いてあったので何度か部品の取り付けを間違えたり接続を間違えたりして挫折しそうになったが、何故かもう一度彼に会わなければいけないような気がして制作を止めることは無かった。
「で、出来た……」
数時間に渡る制作を経て、異次元ワープ機は遂に完成した。巷で流行のスマートフォンのような見た目のワープ機はいままで予想していたものよりはるかに未来的なものだった。これは、僕の人生を変える旅になる。心のどこかでそう感じでいた。
僕は”家”の中にある旅に役立ちそうなものを全て鞄に詰め込んだ。
準備は出来た。もう一度部屋の中を見回す。またここに帰ってくるのはいつになるか……。一年後、十年後、もしかしたらもうここには戻らないかもしれない。そう思うと少し寂しくなった。僕は一度、深く礼をした。
ワープ機の電源を入れる。ついに、始まるのか。不安と希望で満ち溢れた心が武者震いを脳に要求する。ワープ機の画面は緑色の文字列で埋まり、その後、強い光が僕の体を包み込んだ。
Episode.05

ずいぶんと長い間眠っていたと思う。まるで空中を浮遊しているかのような気分だった。ただ、ゆらゆらと。
――ねぇ、大丈夫?
煩いなぁ。静かにしてくれよ。眠いんだ。
――ねぇったら。
やめて。後五分……。
――もう。こうなったらもう……。
「セイッ」
僕はなにやら床に落ちたようだ。ふかふかした所から冷たくて硬い所へ。僕は頭に強い衝撃を受けて目を覚ました。
「うお……!!」
「やっと起きたね……。大丈夫?気分悪くない?」
「えっと、ここは……」
白い肌に銀色の髪。身にまとった暖かそうな洋服。そんな綺麗な女の子が僕に向かって話しかける。辺りを見回せば一面、見たことも無いような煉瓦造りの家だった。
木で作られた家具に古そうな食器棚。見るからにおとぎ話の様な感じだった。
「あなた、家の前に倒れてたのよ。だから、家につれてきたの」
そう言われて僕はふと気を失う前の記憶を取り戻す。そうだ、僕は……。
「あぁそっか……。ワープ機で飛んで……ってじゃあここ何処!?」
「……?ここはアウル王国よ?」
『アウル王国』とは聞いた事も無い名前の国だった。少なくとも僕がいた国の地図や歴史書にはなかった名前だ。ということは……。
「成功、した……」
どうやら無事にワープが成功したらしい。体を見ても腕が消失していたり流血したりという酷い外傷も見当たらない。歴史上の物理学者達が一度は考えたことを僕が無事にやってのけた。そう考えると胸に何か熱いものがこみ上げてくるのがよくわかった。
「で、君。大丈夫?」
彼女のその言葉で僕は我に帰る。
「あ、はい。大丈夫です。ごめんなさい、ありがとうございます」
「いや、いいんだけど。心配で家につれて帰ってベッドに寝かせておいたんだけど……。そしたら今日のいままで起きなくて」
彼女は呆れ顔でそういう。なんだかとても申し訳なくなる。
「そうだったんですか……すみません。ご迷惑おかけました」
「いいのよ。困ってるときはお互い様。それよりお腹へってない?」
そういうと彼女は椅子にかけてあったエプロンを身に纏って台所に向かった。
「そんな、大丈夫ですよ。すぐに荷物まとめて……」
――ぎゅるるる。
断ろうとした僕の言葉を台無しにするかのようにして僕のお腹は自分の空腹を音で知らせてくれた。なんてタイミングが悪いお腹なんだ。僕は自分を静かに睨んだ。
「やっぱり。おなか減ってるんでしょ。ちょっとまっててね」
「ありがとうございます……あ、僕ハルトっていいます」
「そういえば自己紹介、まだだったわね。私はユフ。雪歌ユフ。よろしくね、ハルト君」
ユフさんはそういうと再び台所にはいっていった。
彼女のいる台所からはおいしそうなコンソメの香りが漂っていた。トントントンと、包丁とまな板がぶつかる音とユフさんの微かな鼻歌が台所から聞こえてくる。これは初めての感覚だった。
見ず知らずの人の家で見ず知らずの誰かと食卓を囲む。今まで住んでいた”家”の中では味わったことのない感覚だった。
Episode.06

しばらくすると彼女は食事を食卓に運んできた。湯気をたてるいい香りのスープと焼いたパンのようなもの、そして見たこともない植物の盛り合わせ。どれもこれも僕が前にいた国にはない食べ物だった。
「さぁ、出来たわよ」
彼女はそういうと笑顔で僕に手招きをした。
「召し上がれ」
「……いただきます」
人の手料理を頂くのは、初めてのことだった。身寄りもいない、友達も数少ない。そんな僕には「人と関わる」ということはほぼ無縁に感じていた。だけれども。それは大きな間違いであったのかもしれない。
今見ている、今体感しているこの現状というのは自分が一歩踏み出してしまえば案外簡単に崩れ、壊れてしまい、そしてまた新しい価値観といて自分の中に構築されていくものなのではないのだろうか。そんなことを思いながら僕は彼女が作ったスープを口に運んだ。
「おいしい……!!」
それはいままでに味わったことのない味だった。甘いような、それでいてしょっぱいような。少なくとも僕が前にいた国ではこんな味はなかった。
「そう、それはよかったわ」
彼女は嬉しそうに微笑んだ。
「君は、どこから来たの?ハルトくん」
彼女は続けて僕に問う。
「えーっと、異次元から?」
ユフさんのその問いに僕は正確に答えることができなかった。なぜなら僕自身が今回のワープしたというこの現状を完全には理解し切れていないからだ。
「あ。だから変な格好なのね」
「変な格好とは失礼な」
「だってそんな生地、見たこともないもの。それにそんな薄着じゃこの国では寒すぎるし、一目見たときに別の国の人ってわかったわよ」
「あ、あはは……」
僕はユフさんに格好を変と言われ少し傷ついてしまい視線を逸らした。窓の外から見える森に葉は付いてなく裸の木々はとても寒そうでだった。ふと"家"からコートを持ってくればよかったと思ってしまった。まぁでも、暑い国にいったらまたかさばって邪魔か。それに僕には体毛もあるわけだし。そんなに問題ではないだろう。最悪耐えられなかったら現地調達すればいいんだもんな。そうだ。うんうん。
「あ、そうだ。ハルト君。君、今日からの宿はある?」
「あ」
そうだった。このままここで何時までもお世話になるわけにもいかない。
「あ、やっぱりきめてないのね」
「実は……」
「それじゃあハルト君、こうしましょう」
彼女は思いついたような顔で人差し指を立てて、こう言い放った。
「しばらく、うちに泊まりましょう。そして私の家事のお手伝いをしてくれる?」
窓の外では夕刻を知らせる鐘の音が街全体に響き渡っていた。
Episode.07

雲ひとつない晴天。洗濯物を干すにはもってこいの天気だった。僕は純白のシーツをパンッと音を立てて広げ物干し竿にかけた。
「あー。いい天気ですなぁ……」
暖かい日差しに包まれ、僕は目を細めていた。
「しばらく、うちに泊まりましょう。そして私の家事のお手伝いをしてくれる?」
彼女は僕を指差してそう言い放ち、そして僕に質問の時間を許さずそのまま話を続けた。
「私も市場とかに出ないといけないから家のことがあまり出来ないの。というわけで取引しない?この国にいる間は家で面倒見てあげる。その代わり家事を少し手伝ってもらう。割といい条件じゃない?」
彼女は笑顔で僕に言い放つ。だがその笑顔は何処か裏があるような笑顔だった。ここでそれに打ち勝つのが真の男というものなのだろうが、残念なことに僕はその圧力にあっさり負けてしまった。
「わかりました。そうします。」
「やった!!じゃあしばらくよろしくね、ハルト君!!」
というわけで今に至るわけである。僕は洗濯物を干し終えて家の中に入った。ユフさんは市場に出てしまっていて家には僕独りだった。景色は変われど独りぼっちというのはどこにでも着いてきて僕を悩ますものなのだな、とふと思う。
なにか、このまま家にいるのはダメな気がした。何かに蝕まれている気がした。僕は壁に掛けておいたアウターを身にまとい、街に出た。
ユフさん曰く、このアウル王国は国自体、山のようになっておりその中でも北から南へ、四段の土地によって構成されているという。北のほうから王族の住む「城」、商売が盛んに行われている「市場」、人々が多く暮す「街」、そして作物や家畜を育てたり人が自由に活動できる「草原」。
この四つにより国が構成されておりそれより南にいくと整備されていないただの森になっているという。
僕は午前中にやるべき仕事を全て終わらせていた為、国の中を少し散策しようと考えた。もちろん深い理由はない。ただ、後ろから付いてきた厄介なそいつを振り払いたいが一心で僕は家の外に出たのだ。僕は国の中央を通っている長い階段をただひたすらに下りた。
数十分は歩いただろうか。降りた先には綺麗な野原が見えた。ユフさんが話すには、ここでは子供や恋人たちがよくで遊んでいるという。
僕は木陰に寝転がって子供たちが元気に草原を駆け回っている。ほほえましいな。子供の元気さというのはうらやましい限りだ。
日向ぼっこも時にはいいものだ。そう思いながら僕は空を見ていた。空は蒼く、広かった。僕が前に居た国ではこんな光景は絶対に見ることができなかったであろう。そんなことを考えていると
「お前」
頭上から若い男の声がした。見上げるとそこには他の民間の人とは明らかに違う服装の青年が僕を見下ろしていた。
Episode.08

「おい、お前」
若い男は再び僕を呼んだ。
「……なんでしょう?」
「このあたりで鍵の形をしたネックレスを見なかったか?大切なものなのだ」
「いや、見てないですね」
当たり前だ。僕はまだここに来て数分しか経ってないのだから。
「そうか。ならいい」
男はそういうと向きを変えて何処かへ行こうとする。何故か心に引っかかるものがあった。このまま放っておいても僕の生活には全く持って支障はないだろう。だけれども。
「あの」
「なんだ?」
「もしよければ、お手伝いしましょうか?……その、探すの。」
ここでほうっておくのは僕の良心が許さなかった。たとえこれ一回っきりの出会いだとしても困ってる人というのには変わりはない。困ってる人は、助ける。昔、ルコさんが僕にそうしてくれたように。
「いいのか?」
「ええ。いいですよ。困ってるときはお互い様、というものです」
「お前いい奴だな!名前はなんと言う?」
彼は嬉しそうな顔で僕に名前を問いた。今までの無表情な顔からは想像できないくらいの満面の笑顔だった。
「僕は、ハルトといいます。」
気が付けば日は丘に沈みかけていて辺りはだんだんと暗くなってきていた。
「あった……!」
草原の中にキラリ光るものを見つけた僕はそれを拾い上げた。
「でかしたぞハルト!」
僕はそれを持って彼のもとへ駆けつけそれを渡した。そのネックレスは綺麗な宝石がついていてとても高価のもののようだった。なるほど。これはなくしてはいけない。
「おお!これだ!これだぞ!」
彼は安心したような笑顔でありがとう、といった。
「お役に立てて嬉しいです。」
「そうだ。まだ名前を言っていなかったな。私はアウル王国の王、リアムだ」
王。僕はこの単語を聞き逃さなかった。僕は今この国の長と話をしていて彼の役に立ち彼と同じ時間を共有したのか。そう思うと僕は少し怖くなった。
「王様でしたか。すみません、昨日着いたばかりだったので」
僕は少し身を引いて王様に一礼をした。すると彼はにっこりと笑い、こういった。
「いやいや、そんなに改まらなくていいぞ、ハルト。私たちはもう友達だ」
Episode.09

ユフさんの家に帰るとユフさんが本を読んで待っていた。
「あら、遅かったわね。どこ行ってたの?」
ユフさんは本を閉じそれを静かに机に置いた。
「すみません、ちょっと街を見ていたらこんな時間に……」
「ふーん……そうなの。じゃあそろそろご飯にしましょうか」
そういって彼女は台所に入っていった。しばらくするとトントントン、と食材を切る音が台所から聞こえ始めた。
包丁とまな板が当たり合う音。木と鉄が当たり合う音。その音は僕の心に刺さっては消え、刺さっては消えを繰り返す。
優しいような、優しくないような。そんな音だった。
「さぁ。できたわよー」
そういうとユフさんはお盆に二人分の食事を持ってきた。皿の上に盛られた料理は昨日に続き僕の見たとのない食材を使った僕の食べたことのない料理ばかりだった。
「じゃあいただきましょうか」
食事の最中に僕は今日とあったことを話した。
王様とあったこと。王様の失くし物を探したこと。そして、彼と友達になったということ。
その話をしているときのユフさんはいつもと違い少し顔をしかめていたと思う。
それに気付いたのは僕が全て話し終えた後だった。いつものユフさんからは連想できないような怖い顔をしていて、彼女はその顔のまま僕の目を見た。そして口をそっと開いてこう話し始める。
「あのね、ハルト君。あの王様はね、酷い人なのよ」
ユフさんは僕の目をしっかり見てそういう。僕の心が少し揺れたのが感じられた。
「……それはどういう意味ですか」
声のトーンが少し下がる。これはなんという感覚なのだろう。得体の知れない黒い何かが僕を包む。ユフさんはとても真剣な顔になり僕に向かって、話し始めた。
「彼は前の王様と王妃様の間に生まれたの。彼には兄弟がいなく王様と王妃様はとても甘やかして育てた。それがゆえにわがままな人に育ってしまった。そして、数年前。王妃様が 病気でお亡くなりになり、それを追って王様も命を絶った。一度に両親を失う辛さは私にはわからないけれどとても辛かったと思うわ。でもそれが引き金となってしまったのかしら……。彼は今まで以上にわがままになり、国民を困らせるようになったの。さっき身寄りが一人もいないって言ったでしょ?それがゆえに彼は誰にも邪魔されず王さまの座を手に入れることが出来た」
僕は彼女の話を黙って聞いていた。頭では理解できなくない話だが心で理解できないようで得体の知れない何かはもっと濃くなり僕を包み込んだ。
「これじゃあ、幸せなのか不幸なのかわからないわ」
ユフさんは哀しそうな目でぽつりとつぶやいた。
Episode.10

次の日の朝は、雨が降っていた。
僕はユフさんより少し早く起きて服を着替え、彼女の家を後にした。
レンガ造りの階段を唯ひたすらに上り続ける。この階段は何段あるのだろう。昔読んだ本に出てきた「日本」という国にある神様を祀る場所(確か本にはジンジャと書いてあった気がする。そのときの僕は『しょうが』と間違えた気もする)の一つにとても長い石段のお話があった気がするけど、それとこれとではどちらが長いのだろうか。そんな事を考えながら僕は長い道のりを 辿った。
上りきった時には僕はもう呼吸困難になってしまうのではないか、と思うぐらいに呼吸が乱れていた。さすがにこれは長すぎると思う。なるほど。この石段の長さがこの国の平和を今まで守ってきたのか。人の知識というのはとても素晴らしいものだ。
辿り着いたのはこの国の王、つまり昨日広場で出会った青年、リアム(この場合はリアム王が正確だろうか)が住む城である。なぜここに来たたかといえば理由は二つほどある。一つは先日彼と会ったときに彼に城に招待されたからである。もう一つは、
「すみません。先日リアム王に城に招待されたハルトという者ですが」
僕は随分とがたいの良い厳つい門番さんに話しかける。彼は僕をじっと見つめ、そっと口を開いた。
「……お前、なかなか面白い服を着ているな」
「ええ。旅をしているもので」
「ほう……おもしろい。城の中でリアム王がお待ちだ。すぐに行くがいい。お主が来るのを待っていたのか、あまり落ち着きが無い様だった」
「わかりました。すぐに向かいます」
リアム王はあれなのだろうか。「初めて彼氏を家に呼ぶ女の子の様なあれ」なのだろうか。
門番さんが重たい扉を開いた。僕は城の中へそっと足を踏み入れた。
お城の中は案外シンプルな造りのようで僕は案外すんなりと王様が待つ部屋にたどり着くことが出来た。彼の居る部屋の扉を開くと彼はとても暖かく迎え入れてくれた。彼はやはり「初めて彼氏を家に呼ぶ女の子のようなあれ」のようだ。彼は目を輝かせて僕にこういった。
「私が城に招いた者がここに来てくれるのは初めてのことだ」